なぜ今、相続登記の義務化なのか?
「親から不動産を相続したが、名義変更(相続登記)手続きは後回しにしている」「何十年も前に亡くなった祖父名義の土地がある」…このようなケースは決して珍しくありませんでした。しかし、所有者不明の土地が増加し、公共事業や災害復興の妨げとなるなどの社会問題が深刻化したため、法改正が行われました。
2024年4月1日より、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。放置すると罰金(過料)が科される可能性があります。この法律改正は、過去に相続した不動産にも適用されるため、多くの人にとって他人事ではありません。
この記事では、相続登記義務化の概要、相続登記を怠った場合にどのようなリスクや罰則があるのか、手続きの流れ、費用を抑える方法、そして今すぐ取るべき対策について詳しく解説します。
相続登記義務化の概要

施行日と対象範囲
施行日:2024年4月1日
対象:土地・建物などすべての不動産
過去に相続した未登記の不動産も対象(経過措置あり)
登記の期限(3年以内)
不動産を相続で取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました。
「相続を知った日」とは、一般的に被相続人(亡くなった方)の死亡日です。
過去の相続も対象になる
2024年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記が義務化されます。 ただし、猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに登記を完了すれば、罰則の対象にはなりません。
遺産分割が未了でも「相続人申告登記」が可能に
「相続人が多くて話し合いが進まない」「遺産分割協議に時間がかかっている」といった場合でも、登記義務を履行できるよう、「相続人申告登記」という制度が新設されました。
これは、所有者不明土地問題の解決を目的として、遺産分割協議が成立する前でも、簡易な手続きで登記義務を果たせるようにするものです。
登記を放置した場合のペナルティ
過料(罰金)の金額
登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※刑事罰ではありませんが、経済的な負担になります。
相続登記を放置する5つの大きなリスク
過料の対象になること以外にも、相続登記を放置することで、様々なリスクが発生します。
リスク1:権利関係が複雑になり、手続きが困難になる
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増えていきます。 例えば、Aさんが亡くなり、その相続人であるBさんも亡くなると、Bさんの相続人(Cさん、Dさんなど)も不動産の権利を持つことになります。 こうなると、手続きには数十人分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となり、時間と費用が膨大にかかります。
リスク2:不動産を売却・担保にできなくなる
相続登記が完了していない不動産は、正式な所有者が確定していない状態です。 そのため、不動産を売却したり、金融機関から融資を受ける際の担保にしたりすることはできません。
リスク3:他の相続人に勝手に売却されるリスク
共同相続人が、自分の持ち分だけを第三者に売却してしまう可能性があります。 もし、悪意のある相続人が単独で不動産全体を第三者に売却し、相手が善意だった場合、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
リスク4:不動産を差し押さえられるリスク
相続人のうち誰かが借金を抱え、その債権者によって不動産の持ち分を差し押さえられるリスクがあります。 差し押さえられた持ち分は競売にかけられ、第三者と不動産を共有する事態になりかねません。
リスク5:固定資産税などの負担は続く
相続登記をしていなくても、不動産を所有している限り、固定資産税や都市計画税の納税義務は発生します。 売却も活用もできないまま、毎年税金だけを払い続ける「負動産」になってしまうのです。
空き家を放置すると固定資産税は何倍になる?知らないと損する特定空家制度
相続登記の手続きの流れ
必要書類
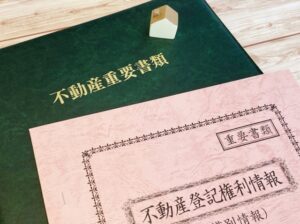
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
不動産の登記簿謄本
固定資産評価証明書
登録免許税の計算例
登録免許税は、不動産の固定資産評価額 × 0.4%。
例:評価額1,000万円の土地 → 税額4万円
費用を抑える方法と相談窓口

自分で書類を集めて申請する。(司法書士費用を節約)
相続登記の無料相談会を利用する。(市町村・法務局)
相続人が多い場合は、早めに司法書士へ依頼してトラブル防止を図る。
今すぐやるべき対策:早めの行動が未来を守る
相続登記の義務化は、所有者にとって負担に感じられるかもしれません。しかし、これはご自身の財産を守り、将来のトラブルを未然に防ぐための重要な措置です。
対策1:まずは不動産の所有者を確認
まずは、ご自身の名義になっていない不動産がないかを確認しましょう。法務局で「登記事項証明書」を取得することで確認できます。
対策2:司法書士への相談を検討する
「何から始めればいいかわからない」「相続人が多くて手続きが複雑だ」という場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。費用はかかりますが、戸籍謄本の収集から登記申請まで、全ての手続きを代行してくれるため、ご自身の負担が大幅に軽減されます。
対策3:相続人同士で早めに話し合う
遺産分割協議がまとまらない場合は、まず相続人申告登記を検討しつつ、早めに話し合いを進めましょう。話し合いが難航しそうな場合は、弁護士など専門家を交えて交渉することも有効です。
まとめ:相続登記は「負」の連鎖を断ち切る一歩
2024年4月からの相続登記義務化は、単なる手続きの変更ではなく、「空き家問題」や「所有者不明土地問題」という社会課題を解決するための重要な法律です。 相続登記を放置することは、過料という罰則だけでなく、ご自身の資産価値を下げ、将来の家族に大きな負担を残すことにつながります。
特に空き家を相続した場合は、登記と同時に活用方法を検討することで、維持費負担や管理の手間を軽減できます。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、まずは所有している不動産の状況を確認し、早めの対策を講じることが、あなたの財産と大切な家族の未来を守る最善の方法です。


